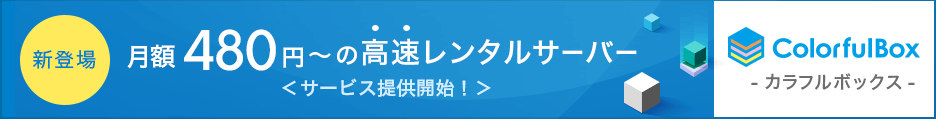
君の愛を奏でて2
「ストロベリータイム2」
【1】
ぼくの名前は藤原彰久。聖陵学院中学校の2年生。管弦楽部でフルートを吹いてる。 そして、ぼくの手には、真っ赤に熟れた山盛りのいちご。 去年の春――いつもすぐ側にいるけれど絶対手の届かない先輩に、甘酸っぱい不思議な気持ちを抱いてしまったあの時――も、ぼくはこうして山盛りのいちごを目の前にしていたっけ…。 「おや、あーちゃんじゃないか。ちょうどよかった。ちょっとこっちへおいで」 その声は、いつも優しい食堂のおばちゃん。 6時間目が体育だったせいで、喉がカラカラになっていたぼくは、部活へ行く前にそれを何とかしなくちゃと、寮を出る前に食堂へ寄ったんだ。 ここには24時間稼働しているウォータークーラーがあるから。…あ、どこかの天然水らしくてすごく美味しいんだ。 それにしても…。 『あーちゃん』って誰? 声をかけられて思わず振り向いてしまったものの、ぼくを『あーちゃん』って呼ぶ人は、この学校の中にはいない。 そう呼ぶのは、ぼくのお母さんだけで、ぼくはもちろん恥ずかしいからそんな風に呼ばれてることなんて誰にも言ってない。 ぼくのことはみんな、『藤原』って呼ぶか『彰久』って呼ぶか、どっちかだ。 なのに、どうして食堂のおばちゃんがそんな風に…。 そう言えば、一人だけいた…。ぼくが『あーちゃん』って呼ばれてるのを知ってる人が…。 それは、ぼくが誰よりも……。 「ほら、こっちへおいでって」 もう一度手招きされた。やっぱり『あーちゃん』っていうのは『ぼくのこと』らしい。 「あ、はい」 おばちゃんが手招きしているカウンターへいくと、『ほらっ』っていう威勢のいいかけ声と同時に、ぼくの目の前にてんこ盛りのいちごが現れた。 「うわ、すごい~」 旬にはまだ早いっていうのに、これはまるで完熟のようにすごくいい香りを放っている。 「これ、持ってお行き」 え? 「えと、あの…」 「これからフルートのパート練習だろう?」 ニコッと笑うおばちゃん。なんでそんなこと知ってるの? 「パートのみんなで分けてお食べ」 …いいのかな? 「遠慮はいらないから」 そういわれてぼくは、嬉しくなって両手でそっとそのお皿を受け取った。 「えっと、ありがとうございます」 「どういたしまして」 そう言っておばちゃんは、綺麗な模様の紙ナフキンをいちごの上にそっと乗せた。 「見つからないように、そっとね」 パチンとウィンクされて、ぼくも笑い返す。 「はい」 「そうそう、葵ちゃんによろしく」 えへへ、やっぱりそういうことだね、おばちゃん。 「はい、もちろんです」 そう言うと、いつの間に側に来たのか、もう一人のおばちゃんが話に交じってきた。 「浅井くんにもよろしくね」 そりゃ、もちろん。 「はい、しっかり伝えます」 元気よく言うと、おばちゃんの手が伸びてきて、ぼくの頭をぐりぐりと撫でた。 「いや~、やっぱりあーちゃんは可愛いねぇ。浅井くんが話題にするだけのことはあるよ」 …え…っ? 「…浅井先輩、が?」 「ああ、そういえば浅井くん、よく藤原くんの話するね」 また別のおばちゃんが交じってきた。夕食時間にはまだまだ間があるから、どうやらちょっと暇らしい。 「そうそう。藤原くんが『あーちゃん』って呼ばれてるって教えてくれたのも浅井くんだよ」 「『藤原って、家では「あーちゃん」って呼ばれてるんですよ。あいつらしくって可愛いでしょ?』…な~んて言ってたねぇ」 そういうと、いつの間にかさらに増殖したおばちゃんたちが『やだー!可愛い~』なんて大騒ぎを始めた。 どうしようかとオロオロしてると、おばちゃんの一人が『ほら、行かないと部活に遅刻しちゃうよ』って言って、騒ぎを止めてくれた。 「…えっと、じゃあ、行ってきます」 もう一度お礼を言って、背中を向けるぼく。 『いってらっしゃ~い!』 ぼくの背中に被ってきたのは、やっぱりおばちゃんたちの楽しそうな大合唱だった…。 いちごを落とさないようにそっと運びながら、寮から伸びる下りの坂道を、ぼくはドキドキしながらちょっと小走りに音楽ホールへ向かっている。 もちろん、ドキドキしているのは小走りになっているからじゃあなくて…。 『浅井くんが話題にするだけのことはあるよ』 『そういえば浅井くん、よく藤原くんの話するね』 ついさっき聞いたおばちゃんたちの話が、頭の中をグルグルと回っている。 …先輩が、ぼくの話を…。 そう思ってさらにドキドキが激しくなったとき、先の方に見えた、高校寮との合流点に、ぼくはその人の姿を見つけた。 …浅井先輩! わぁ…初めてみた。ついこの前に配られたばかりの新しい制服――ベストを着ている姿。 かっこいいや…。 今日はちょっと肌寒いから、ぼくも着てるんだけど、全然感じが違う…。色もデザインも一緒なのに。 でも、声をかけようとして喉まででかかった先輩の名前は、そのままぼくの胸の中へ引きずり戻された。思いっきり強引に。 だって、側には…。 「こらっ、やめろってば」 そう言いながらもちっとも迷惑そうでない先輩の声。 じゃれついているのは奈月先輩じゃない。 奈月先輩ならいいんだ。だって、先輩は、奈月先輩のものなんだもん。 でも、今先輩にじゃれついてるのはあの人。 遙か遠く、ヨーロッパからわざわざこの学校へやって来たのは、先輩を追いかけてきたんだって言う噂の、アーネスト・ハース先輩。 ファミリーネームで呼ぶと、先輩は『チッチッチ』と人差し指を振ってにっこり笑う。 そして言うんだ。 『アニーでいいよ』って。 だから下級生はみんな、『アニー先輩』って呼んでる。 アニー先輩は誰にでも同じように優しい。 下級生にも全然分け隔てなく同じ優しさで接してくれて、上級生には――実際には最上級生の年齢らしいんだけど――とても礼儀正しくて、それでいて優しい。 だから誰からも人気がある。管弦楽部の生徒はもちろん、そうでない生徒にも。特にメロメロなのはオーボエパートのみんなだけれど。 もちろんぼくだって、アニー先輩のことは大好き。 ぼくなんかのフルートにだって、いつも細かく丁寧なアドバイスをくれて、そして最後にはこう言ってくれるんだ。 『あきひさの笛はとってもステキだよ』って。 でも、今みたいに浅井先輩にじゃれている先輩を見ると、ちょっと変な感じ。 だって、浅井先輩は奈月先輩のものなのに。 だから、ぼくだって浅井先輩のことをただ、『先輩』として尊敬して……好きだな……って思ってるのに。 なのにアニー先輩はそれを知っていて、それでも浅井先輩にああやってちょっかいをかけるんだ。 『だいすきだよ、ゆうすけ』って。 それってずるい…とぼくは思ってしまう。 好きな人が今、幸せでいるんだったら、邪魔しちゃいけないんだよ。 横から取ろうなんてしちゃダメなんだよ。 …だけど、もちろんぼくに、そんなことを言う勇気なんて無い。 だから、いつも遠くから見ているだけで…。 そしてぼくは、パート練習の時も、なんだか気軽に話なんて出来なくなってしまって。 それはなぜか、アニー先輩とじゃなくて…そう、浅井先輩と…。 だって、先輩…最近なんだかちょっと機嫌が悪そうなんだ…。 「藤原先輩…」 あんまり時間がないって言うのに、先輩たちの姿を見かけてしまって思わず足を止めていたぼくの後ろから、遠慮がちに声がした。 振り返るとそこには、ぼくより軽く頭一つ以上大きい、ぼくにとって『始めての』後輩の姿があった。 「あ…初瀬くん」 初瀬英彦くん。こんなに大きいのにぼくの後輩。まだ中学1年生。 「…あの、どうかしましたか?」 いつも、とても遠慮がちにかけてくれる声。 初めて会ったときはびっくりしたけれど――だってぼくは、ぼくみたいな小さな後輩を想像していたから――初瀬くんはいつも静かで、いつも親切だから、いつの間にかぼくは初瀬くんが隣にいることに不思議な安心感を覚えるようになっていた。 「あ、ううん、何でもないよ」 言いながら視線を戻したけれど、もう、視界には先輩たちの姿はない。 だから、ぼくはちょっとため息をつきながら、また初瀬くんを見る。 「…いこ…」 「…はい」 初瀬くんは身体に似合わない小さな声で返事をして、それから今度は何も言わずにぼくの手から、いちごが山盛りになったお皿を取った。 「両手が塞がっていたら危ないですよ」 初瀬くんは優しい。 ほら、こんな風に、いつでもぼくの荷物を持ってくれたりするんだ。 「でも、初瀬くんだって…」 言いかけて、ぼくは言葉を切った。 てっきり初瀬くんも、そのお皿を両手で持つだろうって思っていたのに、片手で軽々と持ってしまったから。 「先輩、急がないと時間が…」 …そうだった。管弦楽部はどこよりも時間厳守。 今日はパート練習だけで、パートの先輩はみんな優しいから、もちろん遅刻のペナルティなんてないけれど、だからこそ甘えちゃいけないんだって、ぼくはこの1年で先輩たちの態度から学んだ。 「うん、急ごう」 そうして僕たちは、それ以上何かを話すことなく、音楽ホールを目指して急いだ。 おばちゃんにもらったいちごはもちろん、みんな大歓迎で、練習前に6人でペロッと平らげてしまった。 先輩も、甘くて美味しいっていってたけど、ぼくにはなんだか…うん、ちょっぴりすっぱかったかも知れない。 去年のいちごよりも…。 |
| 【2】へ |