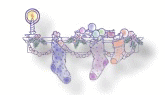
2005年クリスマス企画 『It chose you.』
〜まりちゃん、大学2年の冬〜
前編
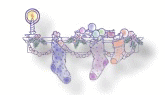
後から何度考えても、あれは本当に不思議な数週間だったと思う。 人間には「不思議体験」に縁のある人間とない人間がいて、俺は明らかに後者のはずなんだけど、あれだけは何とも説明のしようがない出来事だった…。  最近では12月に入るずっと前からクリスマス商戦は始まっているらしく、10月31日のハロウィンが終わった次の日には、もうディスプレイがクリスマスに変わってる店もあったりして、気ぜわしいったらありゃしない。 その所為で…って人の所為にしちゃいけないんだけどさ、俺は『まだまだ早い』なんて結構のんびり構えていて、クリスマスプレゼントの用意ってヤツに出遅れたわけだ。 智なんか、もうすでに用意してるみたいだったよな…。 ま、あいつの場合、万事にそつがないからな。 そんなわけで俺も急いで用意を始めたんだけど、今年は意外に早く、お父さんや秘書さんたち、それにうちの両親…なんてのにはいいものを見つけてホッとしたんだけど、どう言うわけか、肝心の智へのプレゼントにいいものがなかなか見つからない。 どうしよう。 ちょっと焦りモードの俺は、大学界隈の店でこれ以上探しても無理だと踏んで、バイト先の付近で捜索を開始した。 あ、俺のバイトは大学生の定番、家庭教師だ。 ま、このあたりの色々はまた語るとして、その家庭教師先の最寄り駅付近には最近ちょとお洒落でこぢんまりした店が増えたって評判で、俺はそれに縋ってみようと思ったわけ。 そして、探し始めて3回目くらいだったか、ふと気になった小道を曲がってみたときに、その出会いはあったんだ。 周囲に埋もれるように建つ小さな洋館。 レンガの外壁にびっしりと蔓が這っているところをみると、夏にはきっと蔦の葉っぱで覆われてるんだろう。 よく見るとそれは、あたりの店がクリスマスの装飾に溢れてる中――店だけじゃなくて、普通の住宅もイルミネーションがキラキラしてて、眩しいったらないんだけどさ――そこだけは季節感から切り離されたようにひっそりと…ううん、ちがうな、イベント事とは違うところで、『冬』って言う季節感に満ちた、小さなウィンドウのアンティークショップだった。 あ、『冬』に満ちた…ってのは、寒々しいって意味じゃなくて、『冬の暖かい室内を思わせる』って意味なんだけど、ともかくそんな雰囲気の店を見つけたんだ。 で、いつもの俺なら、こういう落ち着いた店にはなんだか入りにくいなあ…って敬遠するところなんだけど、この時はそんなことこれっぽっちも思いつかなくて、俺は誘われるようにその店の小さな木製のドアを開けたんだ。 カラン…と小さくドアベルがなった。 中へはいると、暖房はなんと暖炉。炎の色が店のくすんだ壁を照らして、なんだかホッとする雰囲気だ。 部屋の灯りはさすがに蝋燭じゃなかったけど、でも控えめな間接照明はどれも暖炉の炎と同じ色で、暖かい。 外観から想像したとおり、中も本当にこぢんまりとしていた。でもたくさんの品物が所狭しと並んでいる。 黒光りしている鳥の格好をしたハサミ、飴色になった凝った細工の籠、真鍮の蝋燭立て、繊細なレースのランプシェード、渋い銀色の写真立て、本当に開くのかどうかあやしそうな錠前…。 一見雑然と置かれているように見えたんだけど、よく見ると、それら一つ一つが『自分の居場所』を得て腰を落ち着けている感じがする。 指先くらいの大きさのものに、ブツブツと小さな穴が開いてるものは何に使うんだろう。結構たくさん並んでるけど。 よく見ようと顔を近づけた時、ふとその横にある腕時計が目に留まった。小さなガラスケースに収まったそれは、とても大切そうに扱われていて…。 象牙色の文字盤。女性用ほどは小さくないけれど、でもいかついほどでもない大きさのそれは、『程良い』って表現がぴったりの感じ。 ベルトは革…だろうか。使い込まれた感じでツヤツヤの茶色なんだけど、ヒビとか切れはない。 なんて言うんだろう…。綺麗…って言葉じゃ当たり前過ぎるかなあ。 そして、かなり古そうなんだけど、確かに時を刻んでいる。 いいなあ、これ。智に似合いそう。 そう思ってもう少し顔を近づけた時。 「いらっしゃい」 背後から声がかかった。 普通だったら飛び上がってるとこなんだろうけど、その声がとても優しかったから、俺は特に慌てたり驚いたりなんかしなくて、静かに振り向くことが出来て…。 そこにいた、柔らかでちょっと甘めの声の持ち主は、アンティークショップに相応しく、英国紳士風のダンディなオジサマ………じゃなくて! 「こんにちは」 振り返った俺に、ニッコリ笑ってそう言ったその人は、茶色の髪に茶色の瞳、背が高くてとんでもなくスタイルのいい……一言で片づけてしまうなら、モデルのような男前だった。 しかも若い。大人びてはいるけれど、どうみても20代だろう。 「あ、こんにちは…」 普段から、智だとか小倉さんだとか長岡さんだとか…とにかく超絶オトコマエを見慣れている俺が一瞬絶句してしまうほどの美形は、若いにも関わらず、タイムスリップしたようなこの店の雰囲気にしっくりと溶け込んでいて、彼もまたこの店の一部じゃないだろうか…って思えてしまうくらいだ。 彼が纏う雰囲気が日本人離れしてる…ってのもその一因だろうと思うんだけど、もしかしたら…いや多分きっと、ハーフかなんかだろう。 「外、寒かったでしょう? こっちへどうぞ」 そう言って彼は、暖炉の前の――これまた年代物の――革張りのスツールを勧めてくれた。 誘われるまま腰を下ろすと、冷えた足先に暖炉の温もりがじんわりと伝わってくる。 「はい、どうぞ」 そう言って、俺の向かいに腰を下ろした彼の手にはマグ。ミルクが湯気を上げていた。 いつの間に…。 「ありがとうございます」 『知らない人にものをもらっちゃいけません』…ってのは、チビの頃からお袋に言い聞かされてきた言葉だけど、わけもなく『この人だったら大丈夫』って気がして、俺は素直にマグを受け取った。 冷え切った手にマグの程良い熱さが気持ちいい。 「あの…いただきます」 そう言うと、彼はまたにっこりと微笑んだ。 薪のはぜる音がする。 俺の20年の人生に、暖炉なんて一回も登場したことないのに、なんだか凄く懐かしい感じがした。 一口飲むと、ミルクからはハチミツの甘さが漂ってくる。 まるで智が作ってくれたような、俺の好みにぴったりの甘さに驚いたんだけど、彼の次の一言で俺は更に驚くことに…。 「甘いホットミルク、好きでしょう?」 えっ…何でっ! 「ど、どうしてわかったんですか?」 「だって、そんな感じするじゃない。少なくともブラックコーヒーは苦手だと思うんだけど?」 …どーせ俺はガキくさいですよーだ。 ちぇ、何だ見た目で決められちゃったのか…って思ったけれど、でも美味しいから許しちゃおう。 ってさ、彼のカップにはストレートの紅茶ってところがまた憎いんだけど。 「高校生?」 優雅に一口飲んでから、彼は俺にそう聞いた。 …やっぱり。まあいいけどね、慣れてっからさ。高3まで『中学生?』とか聞かれてたことを思えば進歩だよな。ぐすん。 「大学です、一応」 「ああ、そうなんだ、ごめんごめん」 大して悪びれずに言うけれど、この人だと全然嫌な感じがしない。 「学校はこのあたり?」 「ええと、駅二つ向こうの…」 「ああ、あそこね」 すぐにわかったみたいだ。大きな私立だし、大体その駅付近にある大学って一つだし。 「…じゃあ、もしかして同い年かな?」 「…ええっ?!」 お、同い年って…年齢が一緒って意味…だよなっ? 「なんでそんなに驚くの?」 思わず大声を上げてしまった俺に、彼も声をあげて笑ったんだけど…。 「だって、オーナーさんじゃ…」 「ああ、違うんだ。俺はバイト。オーナーはあっちこっち飛び回ってて、おかげで俺を雇う前は、この店、開店休業状態だったんだ」 そうなんだ。あまりにも店の雰囲気と一体になってるから、俺はてっきり彼がオーナーだと思いこんでた。 「じゃあ、大学生?」 念のため聞いてはみたものの、同い年と言ったのだからそうだろう。でももし4年生だったら2つ上だし、院生ってこともあるよな。 って、思ったのに。 「そう、大学1年生」 あろうことか、彼はそう言った。 「……はあっっ?!」 嘘だろー! 「もっと上に見えた?」 こくこくと頷く俺。 「あはは、でも残念ながら、現役合格の1年生。19歳だよ」 …ってことは…。 「…俺、2年…、はたち…」 …ってさあ、そんなに目をまん丸にしなくてもぉ…。 「…や、ごめん、まさか年上とは思わなかった」 …そりゃそうだろ。俺だって、まさか俺の方が年上だとは思わなかったし…。 ま、しかたねえや…と、少しぬるくなってきたミルクをもう一口飲んで、チラリと視線を流した先には、さっき目に留まった腕時計が。 たくさんの小物たちの間に埋もれそうな感じで置いてあるのに、何故かそこだけ目に付くような気がして、俺は視線だけじゃなく身体も少しそっちへ向けてよく見ようと目を凝らした。 うん、やっぱいい感じ。 ちょっとお洒落で、でもこれ見よがしじゃなくて、色もデザインもシンプルな服が多い智の腕に似合いそう。 でも、さすがに高そうだよな。 俺、ブランドの事は元々全然興味がなくて詳しくもないけれど、安くないだろうってことって事は想像がつく。 古いけど、綺麗に手入れがされてあるようだし、何より、今まで大切にされてきた…って感じがありありと伺えるから。 「気に入った?」 穏やかで優しいで尋ねられ、俺は素直に頷いた。 「うん、すごく。…でも、きっと高いよね」 そうは言ってみたものの、この時の俺に具体的な購入計画はなかった。だって、絶対高いに決まってると思ったから。 俺、プレゼントとかそういう類のものを買うためにバイトをしてるから――日々の小遣いは、お父さん『甘やかし放題』のおかげで全然心配要らない状態だから――それなりに結構貯めてんだけど、それでもこれにはきっと手が届かないだろう。 なんてったって、アンティークだ。良いアンティークは高いものと相場が決まってる。 でも、彼の返事は意外なものだった。 いや、『ううん、安いよ』とかいうんじゃなくて…。 「うーん、どうかなあ」 「へ?」 どうかなあって、なに、それ。 俺が呆けていると、彼は小さなガラスケースからその時計を取り出した。そして、俺の手を取ってそっと乗せる。 わあ…なんだか触った感じも気持ちいい。金属部分は冷たいはずなのに、なんだか暖かみを感じて。 「いや、実はここの商品って値段が付いてないんだ」 時計を完全に俺の手に預けて、彼はそう言った。 ちょっと待った。値段がない……ってことは、ここに並んでるのはむちゃくちゃ希少価値の超高級品ばっか…? ほら、『値段の付けようがない』とかさ……。 …ええっと。そんなものに触ってて、万が一壊しちゃった日には…。 掌のものが急に怖くなって、俺は慌てて返そうとしたんだけれど、彼は『あはは』とまた声をあげて笑った。 「そんなに怯えなくてもいいって。値段がないのは、オーナーが相性をみて値段を決めるだけだから」 「相性?」 何と、何の? 「そう。このアンティークたちが、その人の元へ行って可愛がってもらえるかどうか。それを見てから値段を決めるんだ。だから、ものすごく相性が良いと判断されたら意外と安い。反対に相性が悪いと見たら、手が出ないほどの値段をふっかける」 …そんな商売アリ…なんだ。信じらんねえ。 「でも、そのおかげでアンティークたちも持ち主になる人間も守られるってわけ」 「守られる?」 どういう意味? 「アンティークはね、人を選ぶんだ。それは、過去に大事にされてきた物ほどそう言う傾向が強くて、気に入らない持ち主の手に渡ったら、そこから早く逃れたいがためにその家を没落にまで追い込むこともある」 …ま、マジ? 怯える俺に、彼はニヤッと笑うと、突然俺の頭を撫でた。 「あはは、ごめんごめん」 …はい〜? 「え〜! もしかして担いだな!」 うわーん。俺、ただでさえ単純なんだからー! 「ううん、半分は本当」 ほへ? 「…どっち?」 思わず睨み上げちゃう俺。だって、智と同じくらい背が高いんだもん。 「まあ、家を没落させてしまう…なんて怪談じみた話はさておき、『アンティークは人を選ぶ』ってのは本当だと思うよ。俺も最初オーナーにそう言われたときはまさかと思ったけど、ここにこうして通ってると、嘘じゃない…って感じるようになったから」 …そうなんだ。 でも、確かにここにいるアンティークたちは、見た目はさておき『ただのがらくた』って感じがあんまりしない。妙に自己主張してるやつらが多いような気がするんだ。気がするだけ…だけどね。 「君もオーナーに会ってみるともっとよくわかると思うんだけど、ただね、そのオーナーに会うのが大変なんだよね、普通は」 「あんまりいないから?」 「そう。買い付けだなんだって、あの人飛び回っててね。特に俺がバイトに来るようになってからは安心してるのか、マジでなかなか姿を見せないんだ。だから、本当に欲しかったら粘り強く通うしかない…かな」 ふうん…。 でも、相性をいうなら、この腕時計と智の相性はいいような気がする。 理由は何にもないし、ただの勘ってヤツだけど。 「通ってみよう…かな」 俺がポツッとそういうと、彼は『そうこなくっちゃ』と言って、俺の肩をポンッと叩いた。 |
| 後編へ続く |
*まりちゃん目次へ*
*Novels TOP*
*HOME*