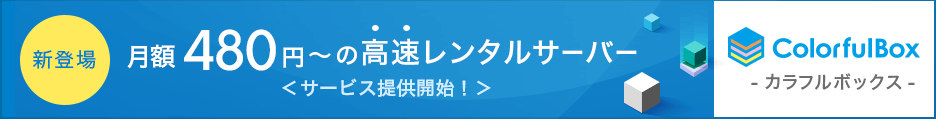
「I Love まりちゃん」外伝
羨望の33階
~11~
僕の出張中、室長は僕の携帯に電話をしてこない代わりに――多分、僕が余裕なく過ごしているであろう事を見越しているんだろう――毎日僕が作成して送信する『出張報告書』への返信に、さりげない気遣いの言葉を必ず加えてくれた。 でも、休暇に入って報告書の提出が必要なくなってからは、僕と室長を繋いでいた唯一の手段も途切れて…。 僕から電話をしようかと何度も携帯を握りしめたけれど、でも、もし邪魔になってしまったらどうしよう…とか、そんなことを考え始めたらきりがなくて、楽しい休暇の最中だというのに、僕のため息はだんだんと増えていくことになった…。 そして、明日の早朝にはここを発って日本に帰るという、ニースでの最後の夜。 「淳、恋人と上手くやっていく秘訣を教えてやろうか?」 昨日までの夜と同じように、広いテラスでのんびりとくつろいでいるときに、春之さんはいきなりそう言った。 「…え」 『恋人と上手くやっていく秘訣』…そんなものがあるのなら、絶対聞いておきたい…。 口を引き結んで頷いた僕に、春之さんは穏やかに笑って言った。 「『対話』…だよ」 「対話…ですか?」 「そう。会話ではなくて対話だ。会話はただ流れていく話し言葉に過ぎない。そして、常に相手の言葉を心に留めつつ交わすのが『対話』だ。それまでまったく別の人生を歩んできた二人が向き合うんだ。行き違いもあるし誤解もある。そんなとき、言葉を使うんだ」 対話…。そう言われて改めて考えてみれば、僕はまだ対話どころか、会話を交わすだけで精一杯かも…。 「対話無しに分かり合えるような関係になるまでには時間がかかる。そしてそんな関係に至るまでに対話を失ってしまったカップルは別れるしかない。人は言葉という素晴らしい道具を持っているんだ。これを使わない手はないんだぞ、淳」 静かに語る春之さんの言葉の一つ一つが胸に沁みてくる。 …あ…もしかして、春之さんも…そうなのだろうか。 会長夫人がここのところまったく家に帰っていないと言う話を誰かが響子さんの耳に入れたらしく、響子さんはとても心を痛めていた。 「あの…」 出来ることなら春之さん本人から事情を聞いて、響子さんを安心させてあげたい……そんな風に考えたんだけど…。 「ん?なんだ、淳」 穏やかに見つめ返されて、僕は続けるべき言葉を見失う。 そんな僕に春之さんは穏やかに笑って見せた。 「相手は私だ。遠慮は要らないよ、淳」 まるで手を差し伸べるようにそう言われて、僕は自然に言葉を継いだ。 「響子さんが……心配しています」 その一言で春之さんは僕の言いたいことを完全に把握したようだ。 「そうか…。一度ちゃんと話そうとは思っていたんだがな…」 ほんの少しだけ瞳を伏せたけれど、春之さんはまた穏やかな視線で僕を見た。 「響子さんは、どこまで知っている?」 「…会長夫人が、自宅に戻っておられないと…」 「それはまた、かなり最新情報をお持ちのようだな」 ククッと、話の内容にはまったくそぐわない笑いを漏らし、春之さんはゆったりと長い足を組み替えた。 「彼女はもう、帰ってこないだろう」 その言葉は『確信』で裏打ちされていた。 「非は100%私にあるからね、いつでも離婚には応じると言ってあるんだが、その気もないらしい。一緒に住むのはごめんだが、自由にしてやる気もない……それがせめてもの彼女なりの仕返しなんだろう」 衝撃的な一言だった。この別居状態の原因を作ったのは、春之さんだった…ということなのか。 呆然と見つめる僕を察したのか、春之さんはまた穏やかに――まったくいつもと変わらない口調で――話し始めた。 「あれは…私が悪かったんだ。そもそも彼女は私の大学での教え子だったんだが、私は覚悟も何もないままに彼女が寄せてくれる好意をただそのまま受け入れた。そして、それでいいんだと思っていた。 だが、智雪が3歳になる前だったか…私は初恋の人に再会してしまったんだよ」 『初恋の人』 僕はその言葉に、大きく目を見開いた。 「納得して別れたわけじゃなかった。大人たちの身勝手な都合で引き裂かれてしまったものだから、燻っていたものが燃え上がるのも早くてね。そして、彼女は敏感にそれを察してしまった。その結果が今に至る…ということだな」 ということは、春之さんは今、その人と…? けれど、現在特に親密な相手がいるようには見えない。 秘書が会長のプライベートまで把握している必要はないんだけれど、そもそも春之さんには『プライベート』なんて無いに等しい。 普段の彼の生活と言えば、睡眠時間以外は仕事をしている…って感じだから。 だから、僕は感じた疑問を口にしてみた。 「その方とは…その…」 「どうにもならなかったよ」 即答…だった。 「どうにもならないとわかっていても……気持ちだけは止められなかったんだ」 僕はこの時初めて、この人の瞳に翳りが差すのを見た。 この人をして、『どうにもならない』と言うことがあるのだろうか。 その疑問は、さすがに言葉には出来なかった。けれど春之さんは答えをくれたんだ。 「彼が背負っているものは、私よりも遥かに大きく…そして、重かったんだ」 その言葉に、僕は返す言葉をもたなかった。 いくつかのキャンドルだけが存在を主張する薄闇の中、沈黙してしまった僕たちの代わりに、遠くの森で何かが鳴いた。 「ここのところ、和彦とちゃんと話をしていないだろう?」 どれくらい経っただろう。沈黙を破ったのは、春之さんだった。 「…はい」 図星だ。 「距離は関係ない。時間も関係ない。声が聞きたくなったら話をすればいい。和彦はお前のすることなら何でも受け止めてくれる」 「でも…っ」 ――何でも受け止めてくれる。 その一言に、燻っていたものが、胸の中で小さく爆発した。 「でもっ、それではダメなんですっ」 「どうして?」 春之さんは、まったく動じることなく、穏やかに微笑んだ。 「僕は、室長に相応しい人間にならなくちゃいけないんですっ。甘えてばかりではダメなんですっ」 でも僕は必死だった。 僕がこれからもずっと彼の側にいるためには、それしかないんだから。 「なんだ。淳は和彦に相応しくないというのか?」 春之さんが目を丸くしてみせる。僕はただ、頷くばかりで。 「何故だ?何故そう思う?」 「…僕は、半人前です。仕事も…なにもかも」 僕は、情けなくて、俯いてしまうしかない。 ふと、春之さんが動く気配がした。そして、ゆっくりとした足取りで、僕の隣へやって来て腰を下ろした。 「いつだったか…」 長くて暖かい腕がそっと僕の肩に回される。 「和彦の一番上の妹……秋葉嬢と話をしたことがあるんだが、彼女は言っていたよ。両親を亡くしたばかりの頃の和彦は、4人の妹たちの親代わりにならなくてはいけないという重圧で、壊れそうなほど張りつめていて、痛々しかった…とね」 …え…あの、室長が…? 考えられない。だって、室長はいつも余裕で、いつも悠然としていて…。 「和彦も、一人で大人になったわけじゃない。周囲に助けられながら7年という年月を重ねて今の立場を築いてきた。 淳、お前はこれから大人になっていくのだから、7年先を行く和彦の力を借りればいい。そして、この先和彦もまだまだ成長していく。お前はそれを追いかける。 その『追いかける』という努力を怠ったときに…」 僕の肩を抱く腕に力が籠もった。 「『相応しくない』という言葉を使えばいい」 春之さんの言葉に引きつけられるように、いつしか僕は顔を上げて、その端正な横顔を見つめていた。 ふと、目が合う。 「幸せになってくれ、淳」 優しい言葉と共に、そっと肩を抱き寄せられ、僕はその暖かさにうっとりと目を閉じて、逞しい肩に頭を預けた。 |
| 12へ続く |
*まりちゃん目次*Novels TOP*
*HOME*